「殺処分ゼロ」という言葉は、非常に強い道徳的インパクトを持つ。
誰もが望む“良いこと”の象徴として広まり、多くの自治体がとりくみ、選挙戦で公約に掲げる候補者もいて、国民の大半もまたそれを無条件に歓迎した。
しかし今、その“成功”の裏で、静かに異変が起きている。
日本各地で、外猫──いわゆる地域猫や野良猫の姿が目に見えて減少しているのである。
その減少は、「保護されたから」ではなく、避妊去勢による子孫を残させない、意図的な少子化政策による。
外猫の存在は、従来の家猫の供給構造そのものであった。多くの飼い猫は、野良として発見され、保護され、家庭に迎えられてきた。つまり、家猫とは、外猫からの自然供給によって成立する文化だった。
だが、「殺処分ゼロ」を制度化する過程で、多くの自治体が猫の“持ち込み制限”を実施し、同時に“野良への餌やり禁止”を条例化した。
獣医師と連携し外猫への避妊去勢を進めた。
これにより、外猫の生存基盤そのものが破壊され、“保護すべき対象”が消えつつある。
さらに問題を複雑にしているのは、避妊去勢の推進が「当然」とされ、それに対して獣医師が何らの抑制も啓蒙も行わないことである。
避妊去勢は、外猫を「増やさない」ための手段として機能するが、過度になれば当然ながら種の絶滅に繋がる。
動物病院は“避妊去勢”をビジネスとして取り込みながら、「個体数を維持する努力」は行わず、「数が減る結果」についても責任を負っていない。
つまり、制度・経済・倫理の連携によって、“殺処分数”は確かに減少したが、実際には“猫の総数”が激減しているという現象が生まれている。
この構造は、目先の道徳性を優先するあまり、長期的な生態系・文化・共生関係の崩壊に繋がりかねない。
アンケート調査では、いまのところ家猫の数はあまり減っていないように見える。しかし一度減少し始めればしばらく止まらないだろう。
暮らしの中に溶け込んでいた地域猫のいる風景は、おそらく戻ることはないだろう。
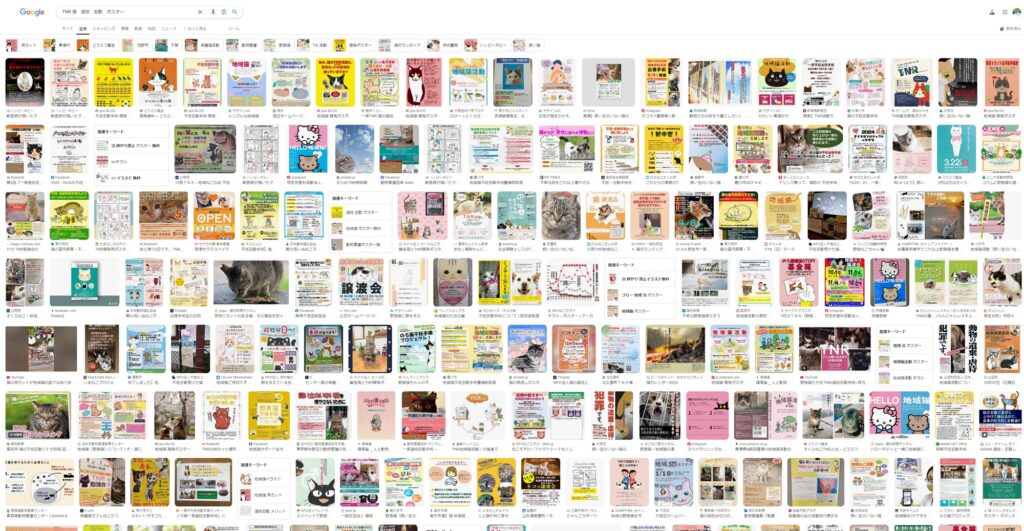
猫の避妊去勢を推奨するポスター
